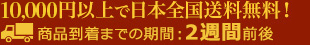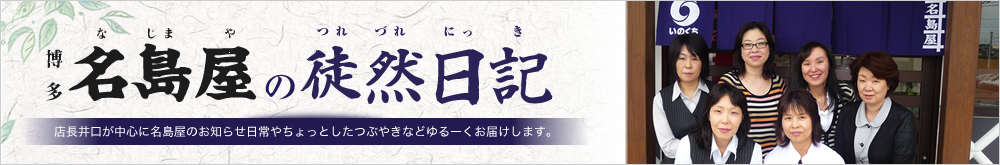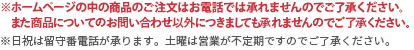桧山先生の料理塾に通ってますが、私は本当に成長のないうかがうだけの生徒のような気が
しておりますが、この本をなにげなく置いてあったテーブルの上で見つけ、読ませていただいたの
ですが、読みながら、すっと心にはいっていくのは、やはり通っていることだろうと改めて思った
次第です。是非少しづつご紹介させていただきます。
桧山タミ先生著 編集発行 福岡市消費流通課 昭和56年3月発行
「幸せの青い鳥はどこにいるのかな」
はじめに
四季にめぐまれた国に住み、その季節の移り変わりを敏感に日常生活の中にとりいれて
きた私達の祖先は、食生活の根本は「自然の法則に」にしたがうことが大切だということを
長い生活のつみかさねで知りました。
それは、身近にある材料を時代の推移と共に他の国の生活の知恵をもたくみにとり入れ、
それぞれの地方色豊な料理をつくり出しているこでもわかります。
そんな大切なことを、いくさに負けたということで捨て去り、自然の恩恵さえ忘れてしまったよう
です。一年中、季節に関係なく材料を手に入れることもできるし、手をよごさずにすぐに食べられる
ものもあり、食べ物は花ざかりの時代です。でもなんだか季節はずれのお花見、造花を眺めて
いるような味気なさを感じませんか?
野原にひとしれず咲いている小さな名もない花の方が、心がやすらぎます。毎日食べるお惣菜
もそんな心のやすらぐものでありたいのです。
上記はこの本の最初の文章です。先生のお料理塾では季節の旬の野菜、果物が使われます。
一番おいしいころのものを知ってほしいと、先生はよく言われます。そうすると、季節の移り変わり
に敏感にもなります。
この本は1月から12月まで月単位でお話があります。少しづつ書かせていただきます。。
名島屋 井口 知子
7月編から
料理のコツは一にも二にもまず材料、料理に適したものを選ぶこと。
そして新鮮なことが大切です。畑からとりたての野菜はすぐに煮え、甘味
がありそれだけでももうご馳走です。
大根は大根らしく葉はよく茂り白い根っこは、ずどんと大きく見えるため
より重くて肌につやがあり、凹凸のない、下の方がすぼっと細くなり、
ひげ根のあるものを。
筍は女竹と男竹があり、女竹のほうがやわらくておいしく、又掘りたては
茹でずに皮をむいてすぐ煮るとえぐみがありません。
地中でグングン大きくなっているのが地面の盛り上がりでわかるのでしょうか。
猿はまだ寒い間にみつけて、穂先のやわらかい一番おいしいところだけを
食べているそうです。
その穂先が黄色のが女竹でキナケン、青色しているのが男竹です。
そして女竹は楕円形、男竹は丸い形をしています。それを知って筍は
選びましょう。
夏が産卵期の多い貝は春はその青春期にあたるので、貝殻いっぱいに
身はふとり味もよく、殻の色さえつやをましています。海水よりうすめの
塩水、それも荒塩をとかした中にやっと貝がかくれる位の中に、貝がかさ
ならにように入れ、暗いところに置きます。
すると貝は安心してチュウ、チュウ潮をふき、砂をはき出します。
塩分は「濃度のうすい方に移行する」を台所ではフルに活用して塩抜きを
しましょう。
そして貝はひな祭りのご馳走に必ず添えられました。これは旬の味と
と共に貝は上下合うのは一つしかありません。巻貝に合う貝の身も一つ
だけです。
母親は娘がお嫁にゆくときに、貝のからのようにぴったり合った人に
めぐり合い幸せになってほしいと女の子の節句、ひな祭りになぞらえて
祈ったのです。
8月編
甘酒饅頭
秋祭り、お櫛田さまのおくんちにお参りして、思いがけなく甘酒のおご馳走に
なりました。いちょうを見上げながらいただいた甘酒の生姜の香りにいろんな
思い出が浮かんできます。
鎌倉時代の末、宋(中国)との貿易の拠点は博多津で、中国の貿易商人も
たくさん住んでいました。宋の豪商、謝国明の援助で宋に渡った聖一国師弁明は
禅を学ぶと共に饅頭や麺の作り方もおぼえて帰国し、帰国後、承天寺を開山
されました。
ですから饅頭にうどんは博多が発祥の地といわれています。その頃の饅頭は
どんなものだったのでしょうか。私たちの学生のころ、祝祭日には必ず紅白の
甘酒饅頭をもらいました。冷えたのは炭火で焼いたり、翌日には油で揚げて
おやつです。
筑後平野でとれる小麦は質が良く、それを宝満川の水で水車を廻し、一子
相伝で粉を挽いていました。その粉で作るうどんはこしがあり、玄海の海で
とれる「いりこ」のだしと良く合い、「博多のうどん」は有名でした。しかし今は
残念ながらなくなってしまいました。
四のつく日だけ聖福寺の門前で昔ながらの甘酒饅頭が売られるとのことです。
年のせいでしょうか、あの饅頭の味が忘れられず、饅頭、まんじゅうと探して
、やっと作り方を教えてもらいました。
まず甘酒作り、少し柔らかめに炊いた米飯を人肌位にさまし、甘酒麹を入れて
よくまぜて温かいところに置き、発酵させ甘酒をつくります。それを幾日も置くと
甘みはすっかりなくなり、ピッリツと少し辛くなってきます。甘みがある間はふく
れません。小麦粉は粉ふるいでふるい砂糖と塩をまぜます。その中に辛くなった
甘酒を耳たぶ位のやわらかさになるまで入れてよくこねるのはパン作りと同じです。
よくねばりがでるまでこね、温かいところにねかせて発酵させます。
倍位にふくれたところでガス抜きをし、小さくちぎったあんを入れて饅頭にまと
めます。それを又、発酵させてふかすとでき上り。その出来上がった時のうれしさ。
しかし甘酒饅頭はこわいのです。体調が悪く身体が弱っている時、心が安定を
かいているときにつくると絶対といっていい位出来上がりは無残です。
そのため毎日が身心共に健康であるようにと心くばりをするようになりました。
酵母菌は人の心がわかるのでしょうか。
一生懸命心をこめて作った饅頭はピカッとひかり、おいしさが違います。
昭和56年3月桧山タミ著
9月編
「さばの生ぐされ」「さばをよむ」とかいわれ、さばは上等の魚の仲間に入れて
もらえませんが庶民にとってはおいしい魚です。そして、去年の秋から冬にかけて
さばに教えられたことがあります。
「秋さばは嫁に食わすな」と秋さばのおいしいのは東京を中心とした諺で、九州で
さばの味がよくなるのはむしろ冬になってからが例年のきまりでした。ところが
昨年は9月にはもう脂ののったおいしい本さばがとれ、しめさばにしてその味のよさ
に驚きました。そしてさばのおいしさに大喜びしただけでなんにも気がつきません
でした。ただ芋好きの私は里芋のおいしいのに出合ういません。里芋もさつま芋
栗、そして新米も味がたりないのに、何故だろう夏は猛暑だったのにと不思議に
思いました。
それから暫くたって猿や猪が人家近くまでおりてきて作物を荒らすとのニュース
や、北洋のソ連船が氷にとじこめられているとのニュースを聞いて、これは大変
とやっと気がつきました。
さばが早く九州にやってきて「今年の冬は寒いですよ、海水が異常に冷えて
ます」と知らせてくれたのに、さばのおいしさに気をとられて気くばりを忘れて
いた食欲のこわさにしまったと思いました。
寒さが厳しいと風邪が流行るに違いない。それには体がひえないような食事を
しなければならない。ところが今年の澱粉質は味が悪い。それは成分、栄養価も
たりないことだ。今年はよっぽど献立に気を配らなくてはならにと、やっと間に合い
ました。
そしてさばに芋、猿が天候の異常を知らせてくれているのに、人々は文明の利記器
だけにたよっている。人間が考え造ったものはけして万能ではありません。それに
プラス自分の持っているあらゆる能力をフルに活用して自分自身が信じられる
人にならなければいけないとさば教えてくれました。
自分の健康は自分でした守れません。
56年3月発行 桧山タミ(桧山たみ料理塾)著